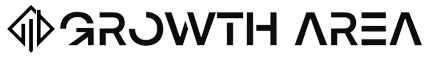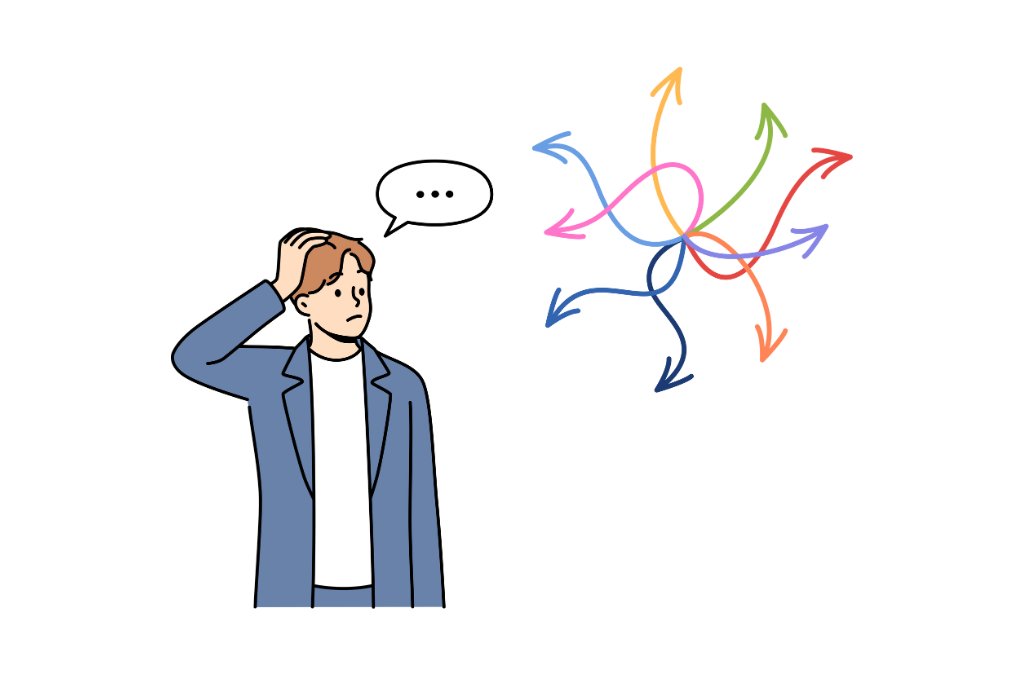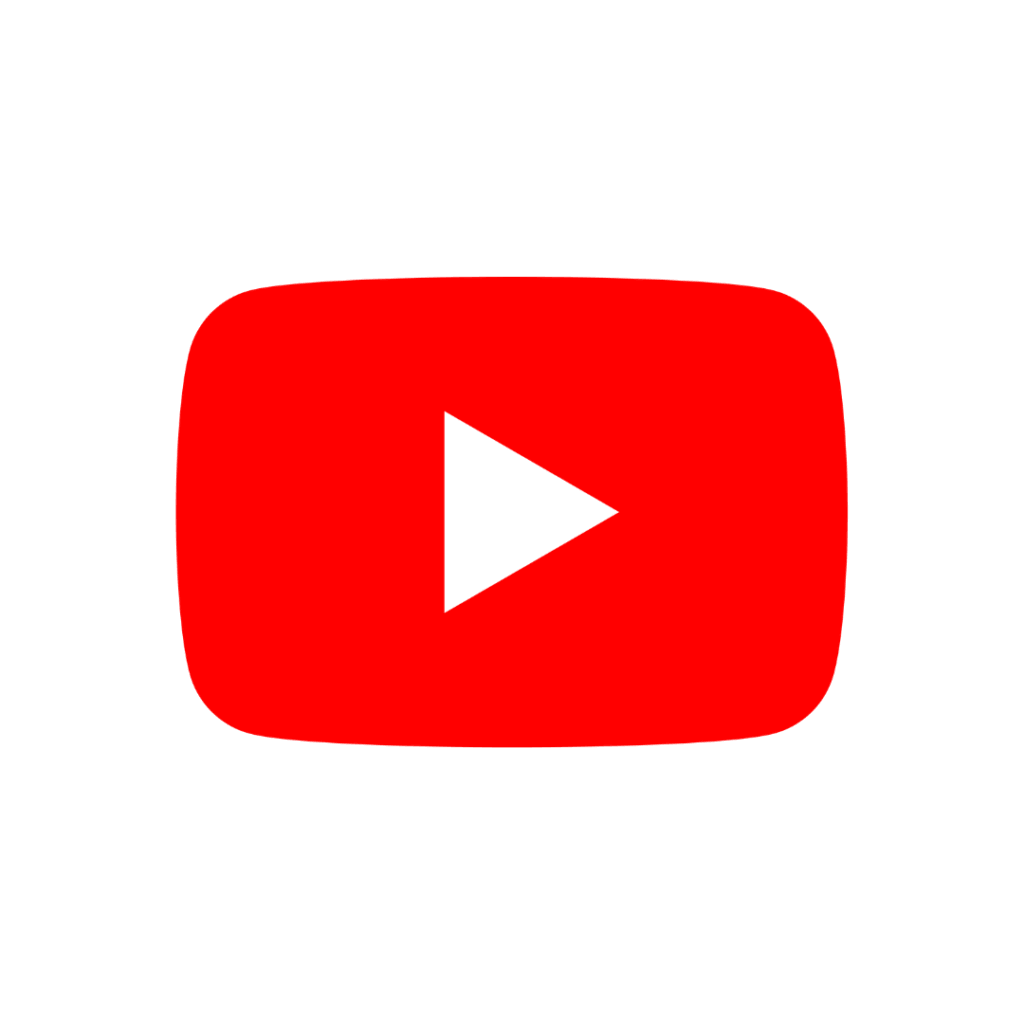「もう辞めたい…でも本当に辞めていいのかな?」
そんな不安でいっぱいな新卒のあなたへ。
この記事では、辞めたい気持ちと向き合う方法から、辞めた後の選択肢まで、後悔しないためのヒントを丁寧にお伝えします。
新卒で「辞めたい」と思うのは普通のこと?

入社3ヶ月以内の離職は意外と多い
「新卒で辞めたいなんて、自分だけかも…」
そう思っている人、意外と多いです。でも実は、新卒の3人に1人が3年以内に会社を辞めているというデータがあります。
特に、入社後の数ヶ月で「想像していた仕事と違う」「ついていけない」と感じて辞める人も少なくありません。
社会人としてのスタートを切ったばかりの時期に悩むのは、ごく自然なこと。
あなただけが特別に弱いわけではないんです。
「甘え」ではなく“自分を守る判断”かもしれない
「辞めたいと思うなんて甘えかな…」と自分を責めていませんか?
けれど、心や体に無理がかかっている状態で無理に頑張り続ける方が、後から大きな代償を払うこともあります。
辞めたいと感じているのは、あなたの中にある“本当の声”。
それを無視せず、自分を守るための行動を取ることも、立派な社会人としての判断です。
無理して続けることが正解とは限らない
「とりあえず3年は続けた方がいい」「我慢も社会人のうち」——よく聞く言葉ですが、その“正解”は本当にあなたにとっての正解でしょうか?
体調を崩してまで、心が壊れそうになってまで働き続けることは、美徳でもなんでもありません。
誰かが作ったルールではなく、“今の自分にとってベストな選択”を考えることが大切です。
新卒が辞めたくなる主な理由
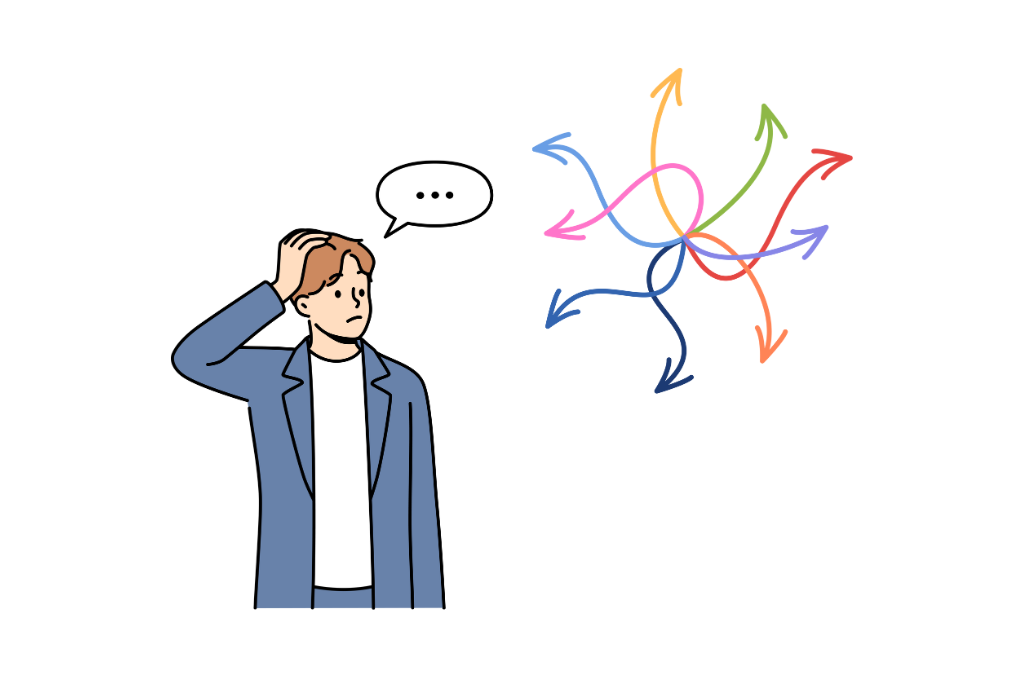
人間関係がつらい・孤独を感じる
会社に入ってまず壁になるのが人間関係のストレスです。
「職場に話せる人がいない」「上司が怖くて毎日ピリピリしている」そんな状況だと、どんな仕事でも楽しくは感じられません。
新卒はまだ社会人としてのスキルも経験も少ないため、孤立感や劣等感を感じやすい時期。
それが毎日続くと、「ここにいていいのかな」と不安になるのも当然です。
仕事が合っていない・やりがいを感じない
「この仕事、全然面白くない」「毎日ルーティン作業ばかりで成長してる気がしない」
こう感じることも、辞めたい理由として多く挙げられます。
就活中は想像で仕事を選ぶことも多いため、実際にやってみたら想像と違ったというギャップは、誰にでも起こり得ます。
それはあなたのせいではなく、経験して初めて分かるものなんです。
思っていた会社と違った(ミスマッチ)
「面接で言ってた雰囲気と全然違う」「残業も多いし、人も冷たい」——
入社してからわかることはたくさんあります。
たとえ企業の説明がウソじゃなかったとしても、“感じ方”は人それぞれ。あなたに合っていなければ、それは立派な理由です。
「向いてない環境で無理に頑張る」より、「自分に合った場所を探す」ことのほうが、よっぽど前向きです。
辞めたい気持ちとどう向き合えばいい?

まずは心と体の状態をチェックしよう
辞めたいと思うときは、心や体に何らかのサインが出ていることが多いです。
たとえば、
- 朝になると動悸がする
- 通勤電車に乗るのが怖い
- 土日も気が休まらない
そんな状態が続いているなら、早めに自分を守る決断をしても遅くはありません。
「自分は大丈夫」と思い込む前に、一度立ち止まってみることも大切です。
「誰かに相談する」だけでも気持ちが軽くなる
一人で抱え込むと、どんどん不安や焦りが大きくなってしまいます。
家族や友人、先輩、第三者のキャリアアドバイザーでもいいので、今の気持ちを言葉にしてみるだけで、思考が整理されることがあります。
特に、「話を否定せずに聞いてくれる相手」に相談することで、自分の中にある本音や本当の理由に気づけることも。
辞める前に“辞めた後の自分”を想像してみる
辞めたいという感情だけで行動してしまうと、「辞めたはいいけど何すればいいか分からない…」と後悔することもあります。
まずは、辞めた後にどうなっていたいか、どう働きたいかを想像してみましょう。
新しい会社に入って、どんな自分でいたいのか。
働く時間・人間関係・やりがい…いろんな視点で理想をイメージすることが、次の一歩につながります。
今すぐ辞める?少しだけ我慢する?判断の基準とは

辞めたくなる原因が一時的か、構造的か
たとえば「今だけ仕事が忙しい」「たまたま苦手な先輩とペアを組んだ」など、一時的な問題なら、もう少し様子を見るのもひとつの手です。
でも、「この部署はいつも人がすぐ辞める」「上司がパワハラ気質」など、会社全体の構造に問題がある場合は、改善を期待しすぎるのは危険です。
原因がどこにあるのかを見極めることが大事です。
「あと○ヶ月だけ頑張ってみよう」も選択肢
迷っているときは、「あと3ヶ月だけ続けてみて、どう感じるか」を判断材料にするのもおすすめです。
その間に何か変化があれば続けてもいいし、変わらなければ辞めるという“期限付きのチャレンジ”は、心の逃げ道にもなります。
無理にズルズル続けるよりも、ゴールを決めて動くことで、気持ちにも余裕が生まれます。
辞めるリスクと辞めないリスク、どちらが大きい?
辞めることで「職歴が短くなる」「周囲の目が気になる」など、不安もあるかもしれません。
でも、続けることで心や体が限界を迎えるリスクもあります。
どちらがあなたの人生にとって大きな損失になるのか。
目先ではなく、半年後・1年後の自分を想像して判断してみましょう。
「辞めたいけど、辞めたらどうなる?」という不安

職歴が短い=転職できないはウソ
「すぐ辞めたら、もうどこにも行けないんじゃないか…」という不安は多いですが、今の転職市場では新卒1年未満の離職でも十分にチャンスはあります。
若手をポテンシャルで採用したい企業はたくさんあり、むしろ「若いうちに行動できる決断力」を評価する企業もあります。
若さは最大の武器。やり直しはきく
20代前半は、まだまだキャリアのスタートライン。
失敗しても、やり直しがいくらでもきく年齢です。
「自分の人生は自分で選べる」ことを忘れずに。
今がダメだったからといって、この先もずっとダメなわけじゃありません。
転職市場では“第二新卒”という枠がある
社会人経験が1〜3年程度の若手を対象にした“第二新卒”という採用枠があるのをご存じですか?
この枠では、経験よりもポテンシャルや人柄、前向きさを重視されることが多いんです。
つまり、新卒で辞めても「やり直せるルート」はちゃんと用意されています。
一歩踏み出す勇気さえあれば、大丈夫です。
辞めると決めたらやっておくべきこと

次の選択肢を決めてから退職する
「とにかく辞めたい!」という気持ちのまま勢いで退職してしまうと、次にどう動いていいかわからず、立ち止まってしまうこともあります。
辞めると決めたら、まずは次にどうするか(転職、学び直し、休養など)を決めてから動くのが理想的です。
「やりたいことがないから辞められない…」と悩む人もいますが、まずは「どんな環境なら働けそうか」「どんなことに興味があるか」をゆっくり探すことから始めてみましょう。
退職の伝え方は冷静&丁寧に
「辞める」と言いづらい気持ちはとてもわかります。でも、社会人として大切なのは、伝え方の“丁寧さ”。
感情的にならず、「自分のキャリアについて考えた結果」という理由で伝えると、角も立ちにくくなります。
直属の上司にまず相談し、退職時期や引継ぎについても誠意を持って対応することで、円満退職がしやすくなります。
引き止められても「自分の意思」を大切に
辞める意思を伝えると、上司や人事から引き止められることもよくあります。
「もう少し頑張ってみたら?」「ここで辞めたらもったいないよ」と言われると、迷ってしまうこともあるでしょう。
でも、その場の空気に流されてズルズル続けた先に、後悔が待っているかもしれません。
引き止められたときこそ、「なぜ辞めたいと思ったのか」を思い出して、自分の意思を大切にしてください。
新卒1年目で辞めた人のリアルなその後

「早く辞めて正解だった」と感じるケース
「もっと早く辞めておけばよかった…」
これは、新卒での退職経験者がよく口にする言葉です。
「辞めた後にようやく心が軽くなった」「転職先で自分らしく働けている」という声も多く、苦しかった環境から抜け出したことで、視野が広がった人もたくさんいます。
大事なのは、“辞めたあと”にどう行動するか。焦らず、自分のペースで次を考える時間が持てるようになります。
「辞めた後のほうが成長できた」という声
ブラック企業や合わない仕事から離れたことで、本来の自分の力を発揮できるようになったという人もいます。
たとえば、
- 接客が得意だったことに気づき、営業職で活躍中
- 自由度の高い職場に転職し、のびのび働けている
- 働きながら通信制大学や資格の勉強を始めた
環境を変えることで、自分の強みや可能性が開花することは珍しくありません。
逆に「もう少しだけ頑張ればよかった」という反省
もちろん、「もう少し周りに相談していれば」「部署異動という選択肢もあったかも」と振り返る人もいます。
だからこそ、辞める前に一度、「本当に辞めるしかないのか?」と自分に問いかけてみる時間は大切です。
後悔しないためには、しっかり考えたうえで行動することが一番のポイントです。
辞めずに環境を変える方法はないのか?

部署異動や上司変更の相談をしてみる
辞めたい理由が「人間関係」や「仕事内容のミスマッチ」である場合は、異動や担当変更で改善される可能性もあります。
いきなり辞める前に、「こういう業務にチャレンジしてみたい」「○○という点に悩んでいる」と相談してみましょう。
もし相談を無視されたり、改善の余地がなければ、そのときに改めて転職を考えれば大丈夫です。
社外メンターやキャリア相談を活用する
今は、キャリアカウンセラーや若者向けの転職サポートを無料で受けられるサービスも増えています。
「今の会社を辞めるべきかどうか」だけでなく、「どういう仕事なら自分に向いてるか」も一緒に考えてもらえるので、視野が広がります。
一人で抱え込まず、第三者の視点を取り入れることで、思わぬ突破口が見えてくるかもしれません。
副業や学び直しで“出口”を探す
もし「今すぐ辞めるのは不安…」という気持ちがあるなら、副業やオンライン講座などで別の選択肢を探す時間を作ってみるのもアリです。
自分に合う働き方が他にあることに気づけたり、「転職=すぐ辞める」ではなく「準備してから辞める」という道もあると分かれば、気持ちがラクになります。
自分に合った職場を見つけるための考え方

「楽しい」より「安心して働ける」が大切
転職先を選ぶとき、つい「楽しそうな会社」「福利厚生が豪華」などに惹かれがちですが、
実は一番大切なのは、「安心して働けること」です。
無理せずに本音で話せる環境、休むときはちゃんと休める職場。
そんな“当たり前”がある場所を探すことが、心の安定にもつながります。
職種より“人との相性”を重視する
仕事内容ももちろん大事ですが、人間関係の良さは仕事の満足度に直結します。
「どんな上司と働くか」「職場の雰囲気は合うか」をチェックすることも忘れずに。
就活や転職活動では、企業のHPや面接だけでは見えにくい部分ですが、SNSや口コミ、OB訪問などを通して、人の雰囲気を見極める努力が必要です。
会社を見る目は1社目で確実に養われる
「失敗した…」と思う1社目でも、得られる学びはたくさんあります。
「こういう職場は合わない」「こういう働き方はきつい」
そういった経験を通じて、“自分に合った会社を見抜く力”が自然と身についていきます。
大切なのは、「1社目をハズしてしまった」と悲観せず、次に活かす材料にすること。
まとめ|新卒でも、辞めたって人生は続く
「辞めたい」と思うのは、甘えでも逃げでもありません。
それは、あなたが“自分の人生をちゃんと考えている証拠”です。
新卒で辞める=キャリアの終わりではなく、むしろスタート地点に立ち直るための第一歩。
大切なのは、今の自分の気持ちを受け止め、未来に向けた行動を少しずつ始めていくことです。
無理せず、焦らず。
あなたのペースで、一歩ずつ進んでいきましょう。